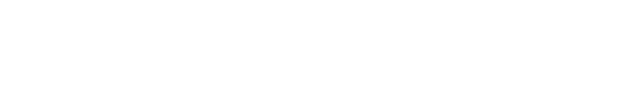ノロウイルスの主な症状|腹痛、吐き気、下痢、嘔吐、軽い発熱について
突然ですが、「ノロウイルス」という名前のウイルスを聞いたことがあるでしょうか。
実際に感染したことのある方や、周囲で感染者が出たという話題を耳にしたことのある方も少なくないと思います。
この記事では、時々ニュースとしても取り上げられるノロウイルスについて、そもそも何なのか、感染した場合の治療法や対処法、感染しないための予防法などを詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- ノロウイルスとは、感染性胃腸炎の原因となる、感染力の強いウイルス
- ノロウイルス感染症の症状として、腹痛、吐き気、下痢、嘔吐、軽い発熱がある
- ノロウイルス感染症への有効な薬やワクチンは未だにない
- ノロウイルス感染症の予防には、加熱処理と消毒の徹底が重要
ノロウイルスとは
ノロウイルスとは、ウイルス性の感染性胃腸炎の原因として知られる、感染力の強いウイルスのことです。ノロウイルスにより引き起こされる感染症が、ノロウイルス感染症です。
ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生しますが特に冬の時期に流行します。
ノロウイルスの特徴から、ウイルスは食品だけでなく、感染者の便や嘔吐物にも大量に含まれているため、二次感染を起こしやすいことが挙げられます。また、わずか10〜100個程度のノロウイルスが体内に入っただけでも感染してしまうため、非常に感染力が強いと言えるでしょう。
ノロウイルス感染症の症状
ノロウイルスに感染した場合、胃の運動神経の低下・麻痺を伴うため、主に以下のような症状を引き起こします。
- 腹痛
- 吐き気
- 下痢
- 嘔吐
また、軽度の発熱(約37〜38℃程度)に加え、頭痛や悪寒、喉の痛み、筋肉痛、倦怠感などの症状を伴う場合もあります。
潜伏期間は1〜2日程度で、症状は比較的軽めです。通常2〜3日で回復します。しかし、高齢者や幼児、病弱な方は、下痢・嘔吐による脱水や窒息、誤嚥性肺炎などで死に至る可能性もあるため、そのような方の感染には注意が必要です。
ノロウイルスの感染経路
ノロウイルスの感染する経路として、以下の経路が挙げられます。
- 経口(糞口)感染
- 接触感染
- 飛沫感染
- 空気感染
ノロウイルスは、経口感染のようにノロウイルスに汚染された食品を摂取して口から感染するケースがほとんどです。しかし食中毒を引き起こしても、原因の食品を特定できない場合が多いと言えます。
原因となる食品の例として、以下のような食品が挙げられます。
- カキなどの二枚貝
- サラダやサンドイッチなどの非加熱食品
- 水や氷
その他、感染者の便や嘔吐物に接触した手指を介して、ノロウイルスが口から入ってしまう糞口感染や、感染者の便や嘔吐物を処理する際などに、空気中に飛び散ったノロウイルスを吸い込むことで感染する飛沫感染。
感染者の便や嘔吐物の処理が不十分の場合、それらが乾燥することで細かい粒子となって空気中に漂い、空気感染するケースが挙げられます。
また、接触感染は、便や嘔吐物だけではなく、感染者が触れたものに触れることでも感染する可能性があるでしょう。
さらに、ノロウイルスの症状が治まっても、その後1週間〜1ヵ月程度は、便の中にウイルスが排泄されることが知られており、二次感染への厳重な注意を行うことが大切です。
ノロウイルス感染症の発生動向
ノロウイルス感染症は、散発発生、集団感染症、食中毒を問わず年間で数百万人の方が感染していると推定されています。これは年間のノロウイルス食中毒患者報告数の数百倍にあたります。感染者の多くを占めているのが、乳幼児・小児の子供です。
一般的な傾向としては、11月から翌年の3月頃まではノロウイルスが流行します。
厚生労働省が感染性胃腸炎について、緊急調査したある時期の集計では、236施設で発生し、患者7,821人、ノロウイルス陽性者5,371人(推定を含む)、死亡者12人となっています。
ノロウイルスに感染したら
現在、ノロウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。下痢や嘔吐などによる脱水症状を防ぐために、市販の飲料水などで水分を補給することが大切です。
飲んでも嘔吐してしまう場合は、早急に医療機関を受診することを推奨します。
便や嘔吐物には、ノロウイルスが大量に含まれている可能性があります。感染の拡大を防ぐために以下のポイントを守って、「素早く」「適切に」処理してください。
- 素早く適切に処理
- 乾燥させない
- 消毒する
ノロウイルス感染症の治療法
現在、ノロウイルスに対して有効な抗ウイルス剤やワクチンがないため、対症療法として、症状に合わせて吐き気止めや整腸剤、解熱剤などの薬を使用するケースが一般的です。
免疫力の低い乳幼児や高齢者は重症化しやすく、脱水症状を引き起こしたり、症状が長引く可能性があるでしょう。また下痢や嘔吐がひどい場合には水分の損失を防ぐために点滴などを行います。
下痢止めについては、ウイルスを体内にとどめ、症状の回復を遅らせることになるため、使用を控えることを推奨します。
脱水症状のサインに注意
ノロウイルスに感染して、嘔吐や下痢などの症状が続く場合、まず注意することが脱水症状です。軽度の脱水症状では、以下のような症状が見られます。
- 皮膚の乾燥
- めまいやふらつき
- 手足などの末端の冷え
脱水症状が悪化すると、
- 尿の回数が減る
- 頭痛やひどい吐き気
- 意識がもうろうとする
- 体がけいれんする
といった症状が起こります。
特に乳幼児や高齢者の場合は、自身ではそのような自覚がなく、症状に気付かない場合もあるため、感染者の周囲の方が脱水症状のサインにいち早く気付いてあげることが大切です。
水分とミネラルのバランスが大切
ノロウイルスによる嘔吐や下痢などの症状が続くと、体内の水分と共に、ミネラル(電解質)も体から失われてしまいます。電解質とは、体の機能調節に必要な成分で、その一つであるナトリウムは、体内の水分調節に大きく関わっています。
しかし、ナトリウムを体内で合成することはできないため、体外から摂取しなければなりません。水分とナトリウムの両方を効果的に補給するためには、通常の水ではなく、適度な塩分と糖分が含まれた「経口補水液」を摂取することが最適です。
嘔吐が続く場合は、1回嘔吐する度に、嘔吐した量と同量程度の経口補水液を飲む必要があります。
また下痢が続いている間は、児童から大人の場合、「経口補水液」を摂取する量として推奨される量は、一日あたり500〜1000mlです。それでも脱水症状が改善しない場合や、吐き気や嘔吐の症状がひどく、口から水分を摂取できないような場合は、点滴で補給する必要があります。
よって、もしその必要性がある場合は、早急に医療機関を受診することを推奨します。
下痢止めの服用
上でも述べましたが、ノロウイルス感染症の症状である下痢を、薬によって無理に止めると、ノロウイルスが腸管内にとどまってしまい、かえって回復を遅らせてしまう可能性があります。
そのため、感染した初期の段階では、むやみに下痢止めを服用しないことを推奨します。ただし、症状が重く、下痢が長引く場合には服用するケースもあるため、医師の診察を受けて、適切な判断を仰ぐことが大切です。
飲食物は回数を分けて摂取
ノロウイルスに感染して、嘔吐の症状が見られる期間は、水分を摂取してもまた吐いてしまいそうな吐き気に襲われるため、摂取することを控えてしまいがちです。
しかし、脱水症状を防ぐためには、少量ずつでも摂取することが重要と言えます。一度にたくさんの量を摂取すると、嘔吐して戻しやすくなるため、数分置きを目安に少量ずつ摂取します。
乳幼児の場合は、スポイトなどの道具を使用することも方法の一つです。この時、冷たい飲料水は腸に負担をかけてしまうため、前もって常温に戻しておいたり、温めたりしてから摂取することを推奨します。
嘔吐の症状が治まったら、消化の良いものを少しずつ食べ始めましょう。
最初は、いつもの食事量の半分以下を目安に、食べられる量から摂取します。量が足りない場合は、一回の食事量を増やすよりも食事の回数を増やし、水分を多めに摂取して補給することが推奨されるでしょう。その後、下痢の症状を見ながら2、3日かけて元の量に戻していきます。
消化の良い食べ物と控えたい食べ物
下痢の症状がひどい時期は、以下のような固形物がなく腸への負担が少ない食品を推奨します。
- 重湯(おもゆ)
- みそ汁の上澄み
- 野菜スープ(具なし)など
症状が少しずつ改善してきたら、
- 米がゆ・パンがゆ
- 煮込みうどん
- みそ汁
- 煮物(ダイコン、ニンジン、キャベツなど)
- 白身魚
- 鶏ひき肉
などを食べて様子を見ましょう。
また油分の多いラーメンや揚げ物、菓子パン、ケーキ、ドーナツや、辛い食べ物、カフェインが含まれる飲み物、乳製品などは腸に負担をかけてしまうため、避けることが大切です。他にも、脂肪の多い豚肉や青魚、食物繊維の多い野菜、香りの強い野菜(セロリ、ニラなど)などは消化しにくく、症状を悪化させるリスクを高めてしまうため、控えることを推奨します。
ノロウイルス感染症への対処法
ノロウイルスに感染した場合、最重要項目として、感染拡大および二次感染の予防が挙げられます。そのための対処法として、以下の4つが挙げられます。
- 手洗いの徹底
- 便や嘔吐物の適切な処理
- 寝具や衣類の入念な洗濯
- 室内や日用品の消毒の徹底
それぞれについて、解説していきます。
手洗いの徹底
ノロウイルスによる汚染や感染を拡大させないための最も基本的な対処法として、流水と石けんでの手洗いを徹底することが挙げられます。
その理由は、アルコール手指消毒薬はノロウイルスへの効果がほとんどないことが挙げられます。さらに、石鹸自体に、ノロウイルスへの効果はないですが、手の脂などの汚れを落とすことができます。それによって、手からウイルスを剥がれやすくする効果があります。
よって、アルコール消毒薬は、すぐに手新井ができない状況などの際の補助手段として活用し、石けんを使用した流水での手洗いの徹底をしましょう。
便や嘔吐物の適切な処理
感染者の便や嘔吐物は適切に処理することが重要です。使い捨てマスクと手袋を着用し、丁寧に拭き取る事を意識して、汚物の中のウイルスが飛び散らないようにし、床に付着した便や嘔吐物は、処理した後、漂白作用のある「次亜塩素酸ナトリウム」を用いて拭き取ることを徹底しましょう。
また、取り残しのないように速やかに処理することで、乾燥したノロウイルスが、空気中に漂い、空気感染することを予防することが重要だと言えます。
次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒液は、500mlのペットボトルを用意し、キャップ1杯分または2杯分の次亜塩素酸ナトリウムを入れた後、水を入れることで作ることが可能です。
また、接触面用と便や嘔吐物などの汚物用では、用いる次亜塩素酸の濃度が変わります。接触面用は、0.02%の消毒液を使用し、汚物用は、0.1%の濃い濃度の消毒液を使用します。
寝具や衣類の入念な洗濯
感染者が使用した寝具や衣類は、入念に洗濯することが大切です。
感染者の便や嘔吐物が付着したシーツなどは、飛び散らないように、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いをすることが大切です。85℃の熱水を使用した1分間以上の洗濯が最も適しています。しかし、使用している洗濯機が熱水を使用できなければ、水洗いをし、次亜塩素酸ナトリウムで消毒を行います。
色物や柄物を消毒する際には、次亜塩素酸ナトリウムには漂白作用があるため、注意が必要です。
また、別の方法として、高温の乾燥機を使用することでも、殺菌効果が期待できます。すぐに洗濯できない布団などは、布団乾燥機やスチームアイロンなどを用いて、よく乾燥させることで効果を期待できます。
室内や日用品の消毒の徹底
ドアノブやスイッチなどの感染者がよく触れる場所は、次亜塩素酸ナトリウムで消毒をするか、消毒用エタノールを使用して二度拭きをしましょう。
感染者が使用した食器類も、同様に次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。トイレやお風呂が、感染者の便や嘔吐物などで汚れた場合は、早急に処理をして清潔に保つことが大切です。
ノロウイルス感染症の予防法
ノロウイルスへの治療法や対処法を述べてきましたが、最も大切なことは、ノロウイルス感染症に対する予防法だと言えます。
基本的な予防法は、手洗いです。
帰宅後、調理の前、食事の前、トイレの後、乳児や高齢者のおむつを交換した後などには、必ず手洗いをし、ノロウイルスを寄せ付けないことが重要です。
特に感染した人の便や嘔吐物を処理する時は、使い捨ての手袋やマスクを着用するなど直接飛沫を吸い込んだり、触れたりしないように注意し、処理した後はしっかり手を洗います。
共用のタオルなどは、他の人が利用した場合、ウイルスが付着していることがあるため、手洗い後は、清潔なタオルやペーパータオルなどで拭くなどの厳重な注意が必要です。
また、手洗い以外に以下の2つが、予防法として挙げられます。
- 加熱処理
- 調理器具の手入れ
それぞれについて、解説していきます。
加熱処理
ノロウイルスは、熱に弱いため、加熱調理は有効な手段の一つです。
ノロウイルスの汚染の可能性のある貝類や野菜などの食材は、食品の中心までしっかり熱が通るように、中心温度85〜90℃以上で90秒以上加熱してから食べましょう。
調理道具の手入れ
調理器具にもノロウイルスが付着している可能性があります。
調理器具は、十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウムで消毒をし、清潔に保つことが大切です。
まな板や包丁、へら、食器、ふきん、タオルなども、使用後はすぐに洗浄し、清潔に保ちましょう。熱湯による加熱(85℃で1分以上)や塩素系漂白剤・消毒剤を使用した消毒が有効です。
まとめ
これまでの内容を踏まえて、ノロウイルス感染症に対する適切な対処を実施できるよう、ノロウイルスとは何なのか、ノロウイルス感染症の症状や治療法、予防法を理解しましょう。
【参考サイト】
■感染対策コンシェルジュ
https://www.m-ipc.jp/what/norovirus/
■いのちをつなぐSARAYA
https://family.saraya.com/kansen/noro/
■国立医薬品食品衛生研究所
http://www.nihs.go.jp/fhm/fhm4/fhm4-nov001.htm
■北海道農業団体 健康保険組合
https://www.hokunoukenpo.or.jp/contents/healthpromotion/03.html
kenei-pharm.com/general/learn/norovirus/5016/
■井上内科
http://www.naika-inoue.com/norovirus.html
■南東北グループ 医療法人財団 健貢会 総合東京病院
https://www.tokyo-hospital.com/archives/14921/
■逓信病院
https://www.hospital.japanpost.jp/health/health201512.html
■水と緑と詩のまち 前橋市
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/eiseikensa/gyomu/5/1/1/4094.html#