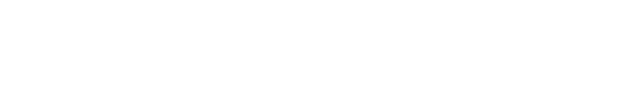ノロウイルスの予防方法|加熱の重要性と消毒について
突然ですが、「ノロウイルス」というウイルスに感染した経験はあるでしょうか。
周囲で感染した人がいたことのある方もいるかと思います。
また、その予防として世の中では、「加熱が大事だ!」と、言われています。この記事では、まずノロウイルスとは何なのか、本当に加熱で予防できるのか、その他の感染しないための予防法などを詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- ノロウイルス感染症の症状として、腹痛、吐き気、下痢、嘔吐、軽い発熱がある
- ノロウイルスを死滅(失活化)させるには、85℃〜90℃で90秒以上の加熱が有効
- ノロウイルスの消毒には、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)水溶液を使用する
ノロウイルスとは
ノロウイルスとは、ウイルス性の感染性胃腸炎の原因として認知されている、感染力の強いウイルスのことで、そのノロウイルスに感染することにより引き起こされる感染症の呼び名が、ノロウイルス感染症です。
ノロウイルスが原因となる食中毒や感染性胃腸炎は、年中感染する感染症ですが、特に冬の時期に流行すると言えます。
ノロウイルスは、食品だけでなく、感染者の便や嘔吐物などの様々な物に大量に含まれているため、二次感染を起こしやすい特徴があります。
また、わずか10〜100個程度のノロウイルスが体内に侵入しただけでも感染してしまうことから、非常に感染力が強いと言えるでしょう。
ノロウイルス感染症の症状
ノロウイルスに感染した場合、胃の運動神経の低下・麻痺を伴います。そのため、主に以下のような症状を引き起こします。
- 腹痛
- 吐き気
- 下痢
- 嘔吐
また、以下のような症状を引き起こすケースもあります。
- 軽い発熱
- 倦怠感
- 頭痛
- 悪寒
- 喉の痛み
- 筋肉痛
潜伏期間は1〜2日程度で、症状は比較的軽度で、回復するまでに要する期間は、通常2〜3日です。しかし、幼児や高齢者、病弱な方の場合、脱水症状や窒息、誤嚥性肺炎などで死に至るケースもあるため、そのような方の感染には注意が必要です。
ノロウイルスの感染経路
ノロウイルスの感染する経路として、以下の経路が挙げられます。
- 経口感染
- 飛沫感染
- 空気感染
- 接触感染
- 糞口感染
ノロウイルスは、ウイルスに汚染された食品を摂取して口から感染する経口感染のケースがほとんどです。しかし、食中毒を引き起こしても原因となる食品の特定ができない場合が多いことが現状です。ノロウイルス感染の原因として代表的な食品は、以下のような食品が挙げられます。
- カキなどの二枚貝
- 水・氷
- 非加熱食品(サラダやサンドイッチなど)
その他、飛沫感染(感染者の便や嘔吐物を処理する際などに、空気中に飛び散ったノロウイルスが呼吸によって侵入することで感染する)、空気感染(感染者の便や嘔吐物の処理が不十分の場合、それらが乾燥することで細かい粒子となって空気中に漂って感染する)のケースが挙げられます。
また、便や嘔吐物だけではなく、感染者が触れたものに触れることでも感染する接触感染や、糞口感染(感染者の便や嘔吐物に手指が接触した際に、ノロウイルスが口から侵入してしまうことで感染する)の可能性があると言えます。
さらにノロウイルスの症状が治まったとしても、その後1週間〜4週間程度は、便の中にウイルスが排泄されることが分かっているため、二次感染への注意が必要です。
ノロウイルス感染症の発生動向
ノロウイルス感染症は、感染者の多くを占めているのが、乳幼児・小児の子供とされており、ケース(食中毒、散発発生、集団感染など)を問わず年間で数百万人の方が感染しているとされています。
一般的に、11月〜翌年3月頃までの約5ヵ月はノロウイルスが流行する傾向にあります。
厚生労働省が緊急調査した、感染性胃腸炎について、ある時期の統計では、以下のようなデータが報告されています。
- 発生施設数:236施設
- 患者数:7,821人
- ノロウイルス陽性者数:5,371人(推定を含む)
- 死亡者数:12人
ノロウイルス感染症の予防法
最も大切なことは、ノロウイルスに感染しないための予防をすることだと言えます。基本的には、ノロウイルスを寄せ付けないための最も重要な予防法は手洗いです。以下のような状況で、必ずこまめに手洗いをすることが大切です。
- 帰宅後
- 調理の前
- 食事の前
- トイレの後
- 乳児や高齢者のおむつを交換した後
特に感染した人の便や嘔吐物を処理する時は、使い捨ての手袋やマスクを着用するなどを使用し、直接飛沫を吸い込んだり触れたりしないように注意し、処理した後はしっかり手を洗いましょう。
洗った手は、清潔なタオルやペーパータオルなどで拭くことも大切です。
共用のタオルなどは、他の人が利用した場合、ウイルスが付着している可能性があるため、厳重な注意が必要です。
また、ノロウイルスに感染しないための予防法として、手洗いの他に以下の3つが挙げられます。
- 加熱処理
- 調理器具の手入れ
- 殺菌消毒
それぞれについて、解説していきます。
ノロウイルスが死滅する温度は?
まず、ノロウイルスの死滅条件(死滅する温度)は、消費者の健康の保護と食品の公正な貿易の確保などを目的として設置された国際的な政府機関であるコーデック委員会が定めた「食品中のウイルスの制御のための食品衛生一般原則の適用に関するガイドライン CAC/GL 79-2012」において、85~90℃で90秒以上と定められています。
また、厚生労働省が作成した「大量調理施設衛生管理マニュアル」のガイドラインでも同様に定められています。
ノロウイルスは、低温・乾燥を好むため、感染力が弱くなるのが、高温・高湿度の環境下です。なおノロウイルスは、他の食中毒を起こすウイルスと比べると耐熱性が高いため、中途半端な加熱では死滅(失火化)できません。
よって、ノロウイルスを完全に死滅(失活化)させるためには、十分な高温での加熱が重要です。
加熱処理
ノロウイルスに汚染されている食品の場合、その食品を加熱することでウイルスを死滅させることができます。ノロウイルスは熱に弱いですが、他の食中毒菌と比較すると、耐熱性があるため、十分な加熱調理をすることが重要です。
ノロウイルスに感染する食品では代表的な牡蠣などの二枚貝の場合は、85℃〜90℃で90秒以上の加熱を行うことで死滅(失活化)できるとされています。
十分な加熱調理がされていれば、感染のリスクを減少させることができるため、特に、抵抗力の低い乳幼児や高齢者向けの調理は、念入りに加熱をするようにしましょう。
調理道具の手入れ
ノロウイルス感染の予防として、食品の加熱処理とともに、調理器具などの加熱処理や消毒が重要です。調理器具の場合は、85℃以上で60秒以上の加熱でノロウイルスを死滅(失火化)することができるとされています。
また、調理器具を使用した後、十分に洗浄し、次亜塩素酸ナトリウムで消毒をし、清潔に保つことが大切です。まな板や包丁、へら、食器、ふきん、タオルなども、使用後はすぐに洗浄し、清潔に保ちましょう。
殺菌消毒
ノロウイルスは、洗面所やトイレ、ドアノブ、電気のスイッチ、冷蔵庫のレバー、水道の蛇口など、様々な場所に付着しています。85℃以上の熱湯、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)水溶液を使用しますが、水溶液は用途や場所によって濃度を変えて使用しましょう。
0.1%に希釈した次亜塩素酸ナトリウム水溶液
0.1%濃度の次亜塩素酸ナトリウムは、感染者の便や嘔吐物、それらが付着した服、リネン類などをビニールなどで密閉処理する際に使用します。
ペーパータオルなどに水溶液を浸して拭き取りましょう。
その際に、飛沫・空気感染を防ぐために、使い捨ての手袋やマスクを使用することも重要です。
0.02%に希釈した次亜塩素酸ナトリウム水溶液
0.02%濃度の水溶液は、洗面所やトイレ、ドアノブなど、たくさんの人が触れる可能性がある場所を消毒する際に使用します。
また、調理に使用する皿やまな板、包丁などの調理器具も、十分に洗浄後、熱湯消毒か0.02%濃度の水溶液での殺菌消毒が効果的です。0.1%濃度の水溶液と同様、ペーパータオルなどに水溶液を浸して拭き取りましょう。
なお次亜塩素酸ナトリウム水溶液は、時間が経つと効果が低下してしまいます。一度に作り置きをせず、毎回使用する際に作って全て使い切りましょう。
ノロウイルス感染症への対処法
ノロウイルスに感染した場合、対処法として注意すべきことは感染を拡大させないことと、二次感染を防ぐことです。二次感染を防ぐための対処法として、以下の4つが挙げられます。
- 嘔吐物や便の処理
- 寝具や衣類の洗濯
- 室内や日用品の消毒
- 手洗い
それぞれについて、解説していきます。
嘔吐物や便の処理
感染者の便や嘔吐物を処理する場合は、使い捨てマスクや手袋を着用し、汚物の中のウイルスが飛散しないように、丁寧に拭き取ることを心がけましょう。床に付着した便や嘔吐物は、漂白作用のある「次亜塩素酸ナトリウム」で拭き取ることが大切です。
また、ノロウイルスは乾燥すると、空気中に漂い、感染することがあるため、取り残しのないように速やかな処理が重要だと言えます。
次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒液は、ご家庭でも作ることが可能です。
- ペットボトル(500ml)を用意する。
- キャップ1杯分または2杯分の次亜塩素酸ナトリウムを入れた後、
水を入れて混ぜる。
また、嘔吐物や便などの汚物用と接触面用では、用いる次亜塩素酸ナトリウムの濃度が変わります。汚物用では、0.1%の濃い濃度の消毒液を、接触面用では、0.02%の消毒液を使用します。
寝具や衣類の洗濯
感染者の便や嘔吐物が付着したシーツなどは、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いをすることで、飛散しないようにしましょう。本来であれば、85℃の熱湯による1分間以上の洗濯が最適だと言えますが、熱湯が使用できない洗濯機であれば、水洗い後、次亜塩素酸ナトリウムで消毒を行います。この際、次亜塩素酸ナトリウムには漂白作用があるため、色物や柄物を消毒する場合は、注意が必要です。
また、高温の乾燥機を使用することで、より殺菌効果が期待できます。布団などのすぐに洗濯できないものは、布団乾燥機やスチームアイロンなどを使用し、よく乾燥させることが効果的です。
室内や日用品の消毒
感染者がよく触れる場所であるドアノブやスイッチなどは、消毒用エタノールを用いて二度拭きをするか、次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。
感染者が使用した食器類なども、同様に消毒を行います。
感染者の便や嘔吐物などで、トイレやお風呂が汚れた場合は、すぐに処理をして清潔に保つことが大切です。
手洗い
ノロウイルスによる汚染を広げないために、最も基本的な対処法は、流水と石けんでの手洗いを徹底することです。
流水と石けんで手洗いの理由としては、アルコール手指消毒薬はノロウイルスへの効果がほとんどないからです。石鹸自体にも、ノロウイルスへの効果はないですが、手の脂などの汚れを落とすことでウイルスを手から剥がれやすくする効果があります。
アルコール消毒薬は、あくまですぐに手を洗えない状況などの際に、手洗いの応急処置として使用しましょう。
まとめ
ノロウイルスとは、ウイルス性の感染性胃腸炎の原因として知られる、感染力の強いウイルスのことです。ノロウイルスに感染した場合、胃の運動神経の低下・麻痺を伴うため、腹痛・吐き気・下痢・嘔吐などの症状が現れます。
また、軽い発熱(約37〜38℃の軽度)に加え、頭痛や悪寒、筋肉痛、喉の痛み、倦怠感などの症状を伴う場合もあります。ノロウイルスを寄せ付けないための予防方法は、手洗い・加熱処理・調理器具の手入れ・殺菌消毒が挙げられます。
ノロウイルスに汚染されている食品の場合、その食品を加熱することでウイルスを死滅させることができます。ノロウイルスは熱に弱いですが、他の食中毒菌と比較すると、耐熱性があるため、十分な加熱調理をすることが重要です。
ノロウイルスに感染する食品では代表的な牡蠣などの二枚貝の場合は、85℃〜90℃で90秒以上の加熱を行うことで死滅(失活化)できるとされています。食品の加熱処理とともに、調理器具などの加熱処理や消毒が重要です。調理器具の場合は、85℃以上で60秒以上の加熱でノロウイルスを死滅(失火化)することができるとされています。
ノロウイルスを殺菌消毒する場合、85℃以上の熱湯、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)水溶液を使用します。次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)水溶液は、「0.1%濃度に希釈した水溶液」と「0.02%に希釈した水溶液」に分け、用途や場所によって濃度を変えて使用しましょう。
次亜塩素酸ナトリウムは、時間が経つと効果が低下するため、全て使い切りましょう。
ノロウイルスに感染した場合、二次感染を防ぐ対処法として、便や嘔吐物の処理・寝具や衣類の洗濯・室内や日用品の消毒・手洗いの徹底が重要です。
これまでの内容を踏まえて、ノロウイルス感染症に対する適切な加熱処理を実施できるよう、ノロウイルスとは何なのか、ノロウイルス感染症の予防法を理解しましょう。また、かかってしまった際の対処法も理解し、万が一の場合に備える準備も怠らないようにしましょう。
【参考サイト】
■感染対策コンシェルジュ
https://www.m-ipc.jp/what/norovirus/
■いのちをつなぐSARAYA
https://family.saraya.com/kansen/noro/
■国立医薬品食品衛生研究所
http://www.nihs.go.jp/fhm/fhm4/fhm4-nov001.htm
■逓信病院
https://www.hospital.japanpost.jp/health/health201512.html
■Foods+plus
https://foods-plus.jp/sanitation/norovirus/
■健栄製薬