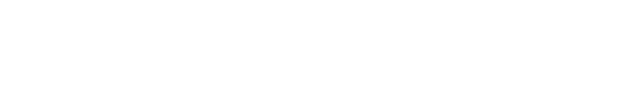手足口病の免疫と再感染の可能性について解説
突然ですが、手足口病という病気を知っているでしょうか。実際に子供が感染したという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インフルエンザの場合、一度感染すると、そのウイルスに対して免疫がつきます。
では手足口病に感染したら免疫はつくのでしょうか。
この記事では、手足口病に感染した場合、免疫がついて再感染しないのか、治療法、予防法とともに詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- 手足口病は、子供が感染しやすい感染症で三大夏風邪の一つ
- 手足口病に感染する可能性のある原因ウイルスは様々で豊富である
- 手足口病に感染した場合、感染したウイルスへの免疫は獲得できるが、その他のウイルスに感染する可能性がある
- 手足口病の予防法として手洗いうがい、消毒の他に、日焼け対策・寝不足厳禁・生理後(女性)に注意することが大切
手足口病とは
手足口病は、子供が感染しやすい感染症で三大夏風邪の一つとして知られています。
手足口病には、未だに直接的効果のある治療薬が開発されていません。よって安静にすることが治療として重要です。
感染した場合、発熱や身体のだるさなど、一般的な風邪の症状が現れます。そして最も特徴的な症状は、皮膚に現れる水疱です。水疱の症状が見られる部位として、以下の3つの部位が挙げられます。
- 手のひら
- 足底(足の裏)
- 口腔内(口の中)
これらの症状から、手足口病と呼ばれています。
手足口病の感染経路
手足口病は、人から人に感染するウイルス感染症で、主に感染経路は、飛沫感染・接触感染があります。感染者の咳やくしゃみに含まれたウイルスを吸い込むことや感染者の唾液、鼻水などに含まれるウイルスが間接的に体内に入ることで感染します。
また、手足口病のウイルスは感染者の便に含まれているため、そのウイルスが間接的に体内に入ることで感染する糞口感染の三つです。
手足口病の原因
手足口病は、ウイルスに感染することで発症します。手足口病発症の原因となるウイルスは様々ですが、主にアルコールなどの消毒剤、熱に強い耐性のあるウイルスで、ノンエンベロープウイルスとも呼ばれている、エンテロウイルス・コクサッキーウイルスが挙げられます。
また、手足口病に感染する可能性のあるウイルスの種類は複数あります。よって、何度も感染する可能性があります。別のウイルスに感染する可能性が残っているため、感染したウイルスに対しては免疫を獲得しても、感染の可能性は消えません。
手足口病の症状
手足口病に感染した場合に見られる、代表的な症状は以下の通りです。
- 水疱の痛み(喉など)
- 手のひら/足の裏の水疱(2~5mm)
- 2~5mmのお尻の周囲の水疱
- 口内の水疱(2~5mm)
- 発熱
手足口病の特徴として、感染してから数日(3〜5)後に、口腔内(口の中)、手掌(手の平)、足底(足の裏)や足背(足の甲)などに水疱性発疹(2〜5mm)が現れ、水疱に痛みを伴うことが挙げられます。足底(足の裏)の水疱の痛みによって、歩行がほぼ不可能になるなど、水疱の激痛によって生活が制限されますが、特に口内は激痛を伴うため、飲食が困難になり、飲食を避けるようになります。
感染者のほとんどは、数日のうちに治る感染症で、個人差があり、症状の見た目は重そうに見えても、水疱の痛みには個人差があり、思いのほか平気な顔をしている子供も見られるため、一概には言えません。症状の箇所も必ずしも、手・足・口の3箇所全てに症状が出るとは限らないため、個人差があります。
手足口病では、感染者の50%に発熱の症状が見られ、そのうち多くの場合は37度台で、38度以上の熱が出るのは、罹患者の30%程度です。
保育園や幼稚園などは熱が下がって、口の痛みがなくなるまで休むことを推奨します。食欲が出て、体調が整ってから行くようにしましょう。
また手足口病は稀に、以下のような症状を合併します。
- 髄膜炎、小脳失調症、脳炎などの中枢神経系
- 神経原性肺水腫
- 急性弛緩性麻痺
- 心筋炎
中でも特に、エンテロウイルス71(EV71)が原因の手足口病に感染した場合には、他のウイルスが原因の手足口病に感染した場合と比べて、中枢神経系の合併症を引き起こす可能性が高いことが報告されています。
発熱
基本的に手足口病では、発熱の症状が現れても37度台で、38度以上の熱が出るのは、感染者の30%程度と稀です。
よって、通常の風邪と同じような対処で、基本的に問題ありません。
手足口病の発熱の症状は、熱が出ていても元気な場合が多く、大体は1~2日程度で下がるケースがほとんどです。
3日以上熱が下がらない場合は、手足口病以外の原因fも考えられるため、早急に小児科への相談をするべきでしょう。
また、発熱の症状が出ていないにもかかわらず、子供がきつそう、普段と様子がおかしいなどの場合も、小児科を受診をしましょう。
下痢・嘔吐
手足口病では、お腹を下して下痢をしたり、吐いたりするケースがありますが、ひどい下痢をしたり、何度も嘔吐してしまうケースは少ないと言われています。
また、手足口病に感染するウイルスは、完治した後も数週間にわたって、長期間便に存在しています。そのため、感染を広げないために、子供のオムツ交換後は、石鹸での手洗いを徹底して行いましょう。
またアルコール消毒が効きにくい種類も存在するため、アルコール消毒と併せて、石鹸での手洗いを徹底することが大切です。
発疹
手足口病の発疹による水疱の症状は、感染してから3〜5日後に出始めます。口の中、手のひら、足底や足背などに2〜5mmの大きさの水疱性発疹が見られ、水疱に痛みがあるのが特徴です。
水疱の症状は、いずれも3日~1週間程度で症状は消えて治ります。手や足にできた痛みや痒みがないことが多いですが、口の中にできた発疹(水膨れや口内炎)に関しては、痛みを伴う場合が多いとされています。
水疱は決して触ったり、引っ掻いたりしないようにすることが大切です。理由としては、水膨れの中には、原因となるウイルスが存在しているため、触れたり引っ掻いたりして潰してしまった場合、感染を拡大させてしまう可能性があることが挙げられます。
また、水疱の症状がひどくなり、治癒するまでの期間が長引いてしまう可能性もあります。よって水疱性の発疹は、触らず、引っ掻かないようにすることが大切です。
喉の痛み
手足口病に感染し、口の中にできた水疱性発疹により、喉に痛みを引き起こすことがあります。そのため、注意しなければならないことは、子供が食事や水分を摂取しなくなることです。脱水症状を防ぐために、水分は十分に摂取し、喉への刺激の強い食べ物は避けて、喉越しが良く、柔らかい食べ物を食べさせることが大切です。推奨される食品の例は、以下の通りです。
- ゼリー
- プリン
- アイス
- 豆腐
- 冷めたおかゆ
手足口病に感染したら
子供が手足口病に感染した場合、近くにない場合は内科でも問題ないですが、小児科を受診するのが基本的です。成人した大人の場合は、基本的に内科を受診します。
手足口病への治療としては、対症療法が用いられます。理由としては、手足口病に対する有効な治療法がないことが言えます。鎮痛解熱薬で、口の中の水疱による痛みを緩和させたり、粘膜保護剤の軟膏による保護が処方される場合があります。
口の中にできた水疱による喉の痛みで、水分を摂取しようとしなくなるため、脱水症状を予防することが大切です。食欲もなくなるため、噛まずに飲み込めるものを推奨します。
保育園や幼稚園の登園などは、基本的に症状が治まるまでは、休むことを推奨します。口の痛みや体の発疹などの症状がなくなり、食欲が出て、体調が整ってから登園するようにしましょう。
手足口病の治療法
結論から言うと、手足口病に感染した場合の特別な治療法はありません。手足口病と診断された場合は、自宅で安静にしながら回復を待つことが推奨されます。
手足口病では、基本的には解熱剤は必要ありません。高熱が出る可能性が低いため、解熱剤は必要ないと言えます。
手足口病の治療として、以下のような対症療法を用います。
- 抗ヒスタミン薬
- 経静脈的補液
水疱による痒みが強い場合は「抗ヒスタミン剤」を処方することで、アレルギー反応を抑制し、痒みや発赤などの症状を和らげます。しかし、水疱に痒みを伴わないケースが多いと言えます。
また経静脈的補液によって、脱水症状を予防することもあります。口内の水疱や喉の痛みによって、飲食物を飲み込むことが難しくなることで、脱水症状を引き起こす恐れがあるため、脱水症状のサインにいち早く気づき、すぐに病院に行き、医師の判断を仰ぎましょう。
手足口病の予防法
手足口病の予防法として、以下のようなものが挙げられます。
- 手洗い
- 手指・身の回りの消毒
- 物の共有をしない
- 温度調節
ウイルス感染で飛沫や手指を介して感染するため、手洗いうがい、手指・身の回りの消毒で感染を予防します。
便の中にもウイルスが存在しているため、赤ちゃんのおむつ交換の後は、しっかりと手洗い・手指消毒を徹底することが大切です。子供に対しては、排泄後はしっかり手洗い・手指消毒をするように指導しましょう。
子どもが鼻をかんだティッシュに触った際や鼻をかむ手助けをした後などにも、手洗いをすることが大切です。
また手足口病に感染している家族がいる場合は、基本的に食器やタオルの共有は避けるべきだと言えます。食器やタオルなどを介して、それらに付着するウイルスへの感染の可能性があるため、ウイルスがまだ存在している期間は、物の共有をしないことが推奨されます。
夏は暑さで体力が落ちてしまいます。その時期に、エアコンで部屋の温度を下げすぎてしまうと、手足口病などの夏風邪に感染しやすくなります。よって、エアコンによる部屋の温度調節にも気を付けることが大切です。
手足口病が完治したら
手足口病に感染し、その症状が完治した後、一安心する方もいるかと思います。インフルエンザは確かに一度感染した場合、その原因となるウイルスへの免疫がつくため、そのウイルスに感染する可能性は基本的にありません。実際に、手足口病に感染した場合も、その原因となったウイルスへの免疫は獲得できるため、同様のウイルスへの感染の可能性は基本的にありません。
しかし手足口病に再度感染する可能性は十分にあります。免疫は獲得できますが、再発の可能性があります。それがなぜなのかということについて、詳しく見ていきましょう。
免疫と再発
手足口病に感染した場合、その原因となったウイルスへの免疫が獲得されます。そのため、同様のウイルスへの感染の可能性は基本的にありません。しかし、感染したウイルス以外のウイルスへの免疫は獲得されていないため、手足口病に感染する可能性は0ではありません。
手足口病の原因となるウイルスは複数あるため、手足口病に感染する原因となる他のウイルスに感染することによって、感染するということです。
よって、感染したことのないウイルスに感染した場合、手足口病を再発する可能性があると言えます。
一度手足口病に感染し、免疫を獲得しても、再発を防ぐために感染予防を意識することが大切です。
上で述べた予防法はもちろんですが、その他にも注意するべきことがあります。注意するべき点は以下の通りです。
- 日焼け対策
- 寝不足厳禁
- 生理後(女性)
まず、日焼けをすると、免疫力が落ちることがわかっています。夏場に海やキャンプ、レジャーに行く場合は、日焼け止めなどの対策をすることが大切です。
寝不足も日焼けと同様に、免疫力の低下を引き起こしてしまうため、風邪やウイルスに感染しやすくなってしまいます。暑さなどで寝苦しい場合は、エアコンなど部屋の温度調節を意識し、快適な睡眠ができるように努めましょう。しかし、温度を下げすぎてしまうと、逆に感染のリスクを高めてしまうため、適温に調節することが大切です。
また、女性は生理中はウイルスの活動の活性化を促してしまう誘発因子となります。生理の際には、十分な栄養と休養を取ることが大切です。いつも以上に体調を気にかけ、無理のない生活を送るように意識することを推奨します。
ウイルスの種類
手足口病に感染する可能性があるウイルスの種類は、以下の通りです。
- エコーウイルス6
- エコーウイルス16
- エコーウイルス18
- エコーウイルス21
- エコーウイルス25
- アデノウイルス1
- アデノウイルス2
- アデノウイルス5
- アデノウイルス6
- パレコウイルス1
- パレコウイルス3
- パラインフルエンザウイルス3
- コクサッキーウイルスA9
- コクサッキーウイルスA10
- コクサッキーウイルスA16
- コクサッキーウイルスB2
- コクサッキーウイルスB3
- コクサッキーウイルスB5
- エンテロウイルス71
以上のことから分かるように、手足口病に感染する原因となるウイルスの種類は豊富にあるため、手足口病に感染して、そのウイルスに対して免疫を獲得しても、その他のウイルスの数から、完治しても決して安心できないことが分かります。
よって、手足口病が完治して、一度感染しているからと安心するのではなく、最初の可能性を少しでも抑えるために、予防の徹底をすることが大切です。
まとめ
これまでの内容を踏まえて、手足口病に感染した場合の免疫について理解し、安心しないようにしましょう。また、再発予防のために適切な行動が取れるようにしましょう。
【参考サイト】
■病気スコープ
■キャップスクリニック
https://caps-clinic.jp/herpangina/
■Doctors File
https://doctorsfile.jp/medication/207/
■厚生労働省 手足口病
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html#:
■太陽クリニック
https://www.taiyo-cl.com/symptoms04
■Medical Note
https://medicalnote.jp/contents/180202-001-MG
■サワイ健康推進課
https://kenko.sawai.co.jp/prevention/201808-02.html
■南福岡さくらクリニック
■徳島大学病院 感染制御部