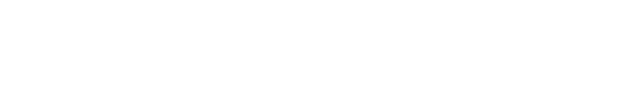乳がんのステージを徹底解説!生存率について詳しく解説します(医師監修)
がんの進行度合いは、一般に病期といいます。この病気は「0期〜Ⅳ期(よんき)」のステージに分類されます。このステージ分類を行うことにより、手術や薬物療法などをはじめとした治療方針を決めたり、生存率の目安を得ることができます。
医師が乳がんの病状を患者さんに説明する際にも、この病期ステージをもとに、乳がんの進行度と生存率について話を進めていくので、知っておいて損はないでしょう。
ここでは乳がんのステージ分類を理解するうえで、知っておくとよくわかる用語の説明をしながら、病期のステージ分類や乳がん生存率について詳しく説明していきます。
>乳がんの疑いがある方はこちら
(無痛のMRI乳がん検診ができます)
目次
8.痛みゼロ、露出ゼロ、被ばくゼロの「無痛MRI乳がん検診」の5つのメリット
乳がんとは
乳がんの病期ステージ分類を理解する前に乳がんについて紐解いていきます。
乳がんは乳房の乳腺組織から発生する悪性腫瘍です。
乳がんは女性で発症するがんのなかでは最も多く、約9人に1人の女性が一生の内に乳がんを発症するといわれています。
自己検診により乳房のくぼみを発見したり、乳房や乳輪に出現した症状が発見のきっかけになることもあります。しかし気づかないことが多いので、乳がん検診を受けることが推奨されます。
なぜなら、乳がんは早期に発見することで、治療効果や生存率も高い病気だからです。
乳房について
乳房はおもに授乳期に母乳をつくる乳腺組織とそのまわりの脂肪組織で成り立っています。
乳腺組織のなかには、「小葉」と呼ばれる母乳が作られる場所と、「乳管」と呼ばれる母乳を運ぶ管があります。
乳房にはリンパ管が通っていますが、それは(1)わきの下、(2)胸骨の内側の内胸リンパ節、(3)鎖骨上にある鎖骨上リンパ節につながっています。
乳がんは上述の乳管から発生することがほとんどですが、小葉からも発生します。乳房の周りのリンパ節や遠くの臓器の骨、肺などに転移を生じることがあります。微小転移があるかないかによっても病期ステージの分類に関わっています。
微小転移とは
微小転移とは、タンポポの種に例えられることが多くあります。
タンポポの種は風に吹かれて遠くの土地まで飛んでいき、発芽に適した場所では花を咲かせます。しかし、芽を出して花を咲かせるまでは見つけることができないですね。
乳がんも、乳がんと診断された時点で微小転移があるかどうかはわからないので、たんぽぽの種に例えられるのです。
転移を生じる頻度は、乳がんが「非浸潤性がん」か「浸潤性がん」か、また前述のステージによっても異なります。
微小転移があるかどうかの推定は、(1)がんの大きさや(2)わきの下のリンパ節を試しに調べた結果、(3)がんの病期ステージの分類などを考慮して行います。
非浸潤がんとは
非浸潤がんはこの乳管や小葉にとどまっているがんのことをいいます。
浸潤がんとは
浸潤がんとは乳管や小葉にとどまらず、突き破って、その周囲に広まっているものを浸潤がんといいます。
乳がんの病期ステージとは
乳がんは、病気の進行により病期であるステージ0期〜Ⅳ期(よんき)に分類されています。
乳管や小葉内から出ずにとどまっている乳がんは、非浸潤がんである0期です。
乳管や小葉から出て広がっている乳がんは浸潤がんであり、Ⅰ〜Ⅳ期に分けられます。
ステージは0期が1番軽く、Ⅳ期が1番重いステージです。
治療には手術や放射線治療、化学療法、薬剤療法があり、早期の発症ではこれらの治療が効果的で生存率が高くなりますが、発見が遅れると致死率も上昇します。
区分けされた病期ステージを知ることで、今後の予後や治療方針が決められるでしょう。
乳がんの検査とは
乳がんの検査では、がんの疑いがあるかどうかを調べ、精密検査では乳がんのさらに詳しい状態を調べるための検査をします。
乳がんの進行により、がんの大きさや全身への転移を調べる検査を追加します。
病期ステージに分類し、治療の方針を確定するためにも検査の内容は不可欠なものです。
1.問診
現在の自覚症状や既往歴や家族歴などを聴取します。医師などの診察により気づかれる症状(他覚症状)も、この問診では重要です。
2.視診
乳房の形や乳頭からの分泌物、乳房の色や形に異常がないかを確認します。左右差や凹みも重要な情報になることがあります。
3.触診
乳房やわきの下のリンパ節にしこりがないかを確認します。
4.マンモグラフィ検査
乳房専用のレントゲン検査です。
乳がんの初期症状である微細な石灰化を捉える点が優れています。そのほかに、局所的な歪み(構築の乱れ)や、しこり(腫瘤)を見つけることもあります。
5.超音波検査(エコー検査)
乳房に超音波を当て、その反射波を画像に映し出して乳房内部の状態を知る検査です。乳房内のしこりの大きさや形(平滑か、ギザギザか)、わきの下や周囲の組織への転移がないか、などを調べます。しこりの硬さを調べることもできます(エラストグラフィー)。また、しこりに流入する血液の量を見ることもできます(カラードップラー)。こういった情報をもとに、良性、悪性の鑑別もできます。
6.造影MRI検査
MRI検査は、しこりの内部性状や広がりについて知ることができる良い検査です。また、両方の乳房全体が写るため、客観的に病変の位置を知るのにすぐれています。造影することにより、がん(悪性腫瘍)が染まります。良性の腫瘍も染まりますが、染まる速度などに違いがあるので、良性と悪性の鑑別にも役立ちます。一般に造影MRI検査は、次項の精密検査で乳がんが疑われ、手術をする前に確認する検査(術前MRI検査)として用いられ、乳癌がどの程度広がっているか、や、反対側の乳房に乳癌がないかの確認をします。ただし喘息などアレルギーのある方は受けることができません。
7.無痛MRI乳がん検診
MRIの撮影法のひとつに、造影剤を使わなくてもがんが写る、拡散強調画像(DWI)という方法があります。これを改良した方法がDWIBS法(ドゥイブス法)です。この方法を中心として、いくつかの撮影を組み合わせたのが「無痛MRI乳がん検診(ドゥイブス・サーチ)」で、最近普及してきました。マンモグラフィーのように乳房を圧迫することなく検査ができるので、痛みがありません。また50歳未満の方に多い高濃度乳房(デンスブレスト)の方でも問題なく撮影ができます。術後の方(インプラントが入っている方)やアレルギーの方でも検査できます。MRIなので被ばくはなく、着衣のままで受けることができます。
乳がんの精密検査(生検;せいけん)とは
1.細胞診
細胞診は病変の一部を採取して顕微鏡で調べる病理検査のひとつで、がん細胞があるかないかを調べます。
2.組織診
組織診は病変の一部を採取して顕微鏡で調べる病理検査のひとつで、細胞より広い範囲である組織の一部を採取し調べる検査です。
細胞診よりも正確な判断ができるため、細胞診をせず組織診から検査する場合もあります。
これらの精密検査は「生検」と呼ばれており、病変部(しこり)を狙って針を指します。このため、マンモグラフィーやエコーの画像を見ながら針を刺します。
乳がんに関連した全身の画像検査とは
乳房から離れた場所の転移を調べるために、CT検査、MRI検査、骨シンチグラフィ、PET検査などの画像検査を行います。
1.CT
CTとは、Computed Tomography(コンピュータ断層撮影)の略で、人体を輪切りにした画像をコンピュータによって再構成します。
全身の撮影ができて撮影時間も短く済みます。ヨード造影剤を用いることが一般的です。画像に歪みがなく、また細かく撮影ができますので、全身の検索には必ず用いられます。
2.MRI
MRIとは、Magnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像)の略で、強い磁石と電磁波を使い、体内の状態を断面像にして描写します。特に骨盤内の病変に関して優れた検出能力があります。また、DWIBS法(ドゥイブス法)と呼ばれる、拡散強調画像(DWI)を改良した方法により、全身への癌の広がりを評価できます(全身MRI)。DWIBS法は、乳癌の骨転移評価に使われることが多くなってきました。この方法は被ばくがなく、安価なので、3ヶ月毎に繰り返し検査可能で、治療しながら経過を見ることができます。
3.骨シンチグラフィ
骨シンチグラフィ検査は、骨にがんが転移しているかを、放射線を発する物質のアイソトープを静脈注射やカプセルを服用し体内に取り込み、カプセルから放出されるガンマ線を体外から計測することによって全身のがんの転移を調べることができる検査です。骨転移検索の定番でしたが、2で示すDWIBS法(全身MRI撮影法)や、4で示すPETなどの診断能が高いことも示されてきたこと、また分解能が低いこと、その割には高価であることから、だんだんと使用頻度が落ちています。
4.PET
PETとは、positron emission tomography (陽電子放出断層撮影)の略で、放射能を含む薬剤を用いる核医学検査のひとつで、放射性薬剤を体内に投与して画像化します。乳癌の転移には、FDG-PETと呼ばれる、ブドウ糖を用いたPET検査を行ないます。
ブドウ糖は、とくに癌などの悪性腫瘍でよく消費されます。良性腫瘍では少し消費されます。このため、癌の位置特定をしたり、良悪性の区別をすることに使われます。また、転移の状況やを判定したり、再発の診断などに利用されます。
>乳がんの疑いがある方はこちら
(無痛のMRI乳がん検診ができます)
乳がん治療とは
乳がんの治療には、手術、放射線治療、化学療法、薬物療法があり、これらの治療を単独で行う場合と複数の治療を組み合わせる場合があります。
病期はがんの進行の程度を表す言葉で、それぞれステージに分類されます。
全身状態、年齢、既往歴、検査の結果などからステージを推定し、総合的に判断したうえで適切な治療を決定します。
乳がんの手術とは
乳がんの手術には、乳房部分切除術(乳房温存手術)、乳房全切除術、腋窩リンパ節郭清、乳房再建術があります。
1.乳房部分切除術(乳房温存手術)
腫瘍をその周囲の正常乳腺を含めて切除します。
乳房部分切除術はがんのある乳腺のがんと、がんのまわりの組織を1〜2cm広くとって切除する手術方法です。
手術後には放射線療法が行われるのが一般的で乳房部分切除術と放射線療法をセットにした治療を乳房温存療法と呼びます。
乳房温存療法は、日本では1980年代の終わりから90年代初めにかけて急速に普及し始めましたが、その頃世界的に行われていた臨床試験では、乳房を全て取っても、乳房を温存して乳房を残しても、転移率や生存率に差がないことがわかりました。
そのため、乳がんは単一でとらえるのではなく全身の病気としてとらえる必要があることが明らかになり、ほかの治療法を組み合わせることが大切だとされています。
2.乳房全切除術
全乳房を切除します。
乳がんのしこりの大きさが4〜5cm以上であり、乳房温存手術にあてはまらない場合乳がんの再発が心配な場合や、乳がんの手術の後に乳房再建を希望する場合に行われます。
また、乳がんのステージ0期でも広い範囲にがんが広がっている場合や、手術前に薬物療法を行ってもしこりが小さくならない場合にも乳房切除術が行われます。
加えて、遺伝子検査により、遺伝性の乳がんであるとわかった場合にも乳房全切除術が選択されることが多いでしょう。
3.腋窩リンパ節郭清
えきかリンパ節かくせいと読み、病気のある部分を切除するとともにわきの下のリンパ節とまわりの脂肪組織も切除します。
がんがリンパ節から血流に乗って全身へ広がるのを防ぐ目的があります。
4.乳房再建術
乳がん切除により形が変わってしまった乳房や、切除により失われた乳房をできる限り取り戻すための手術を乳房再建術といいます。
乳房再建術を行うことにより乳房の喪失感が軽くなり、下着着用時の補正パットが不要になるなどの日常生活での不都合が減少します。
乳房再検査手術の時期により、一次再建と二次再建に分けることができます。
移植には、自分の組織の移植によるものとインプラントによるものに大きく分けられます。
・一次再建
乳がん切除と同時に再建までの手術を行う方法です。
入院が一度で済む大きなメリットがあります。
・二次再建
手術や化学療法などが一段落したところで改めて再建を行う方法です。
全乳房切除後の再建や、部分切除術後の変形の修正なども行います。
乳がんの放射線治療とは
放射線療法とは、がん細胞が正常細胞に比べて放射線に弱いことを利用した治療方法で、がん細胞のある病巣部に放射線を当ててがんを治療する方法です。
・放射線治療の目的
乳がん手術後の放射線療法の目的は、温存した乳房や周囲のリンパ節の周囲に残ったがん細胞が増えて再発するのを防ぐためです。
手術の目的は目に見えるがんを取り除くことですが、術後の放射線療法の目的は手術で取りきれなかった可能性のある目に見えないがんを一切なくすことです。
乳がんの薬物治療とは
乳がんの薬物療法には、主に化学療法、ホルモン療法薬があり、病期であるステージやリスクなどに応じた治療が行われます。
・薬物療法の目的
1.再発の危険性を下げる
術前薬物療法
術後薬物療法
2.手術前にがんを小さくする
術前薬物療法
3.手術が困難な進行がんや再発に対して延命や症状を緩和する
・化学療法の目的
乳がんの化学療法の治療の目的はがん細胞を一切なくすことです。
化学療法の種類には、抗がん剤や分子標的薬があります。
1.抗がん剤
乳がんの手術後に抗がん剤を行うのは、がん細胞が血流に乗って体内のあちこちへ運ばれる微小転移となっている可能性があるためです。
抗がん剤はがん細胞の増殖を抑える作用をしてその細胞を死滅させる役割があります。
しかし正常な細胞にも影響を与えてしまうため、全身に嘔気や脱毛、食欲不振など、さまざまな副作用が現れる傾向があります。
2.分子標的薬
乳がんの分子標的薬は、がん細胞に特異的にみられる分子を標的とした薬です。
乳がん細胞に効果的に作用します。
・ホルモン療法薬の目的
乳がんには体内の女性ホルモンの影響で、がん細胞の増殖が活発になる性質のものがあります。
ホルモン療法薬により乳がんの細胞内でエストロゲンという女性ホルモンと結びつくのを妨ぎます。
また、エストロゲンがつくられないようにして、がん細胞の増殖を抑えるホルモン療法薬もあります。
>乳がんの疑いがある方はこちら
(無痛のMRI乳がん検診ができます)
乳がんの病期ステージ分類とは
乳がんのがんの進行度は病期といい、ステージ0〜Ⅳ期に分類され、ステージはローマ数字を使って表記されます。
乳がんの病期であるステージはしこりの大きさ、乳房内での広がり具合、リンパ節の転移の状況、他臓器への転移があるかによって分類します。
乳がんの病期(ステージ)分類
|
ステージ |
しこりの大きさや転移の状況 |
|
0期 |
非浸潤がんか、あるいはパジェット病できわめて早期のがん |
|
Ⅰ期 |
がんの大きさが2cm以下で、リンパ節や他の臓器に転移していない |
|
ⅡA期 |
がんの大きさが2cm以下で、同じ側のわきの下のリンパ節は固定されておらず動く、もしくは、がんの大きさが2cmを超え5cm以下で、リンパ節や他の臓器への転移はない |
|
ⅡB期 |
がんの大きさが2cmを超え5cm以下で、同じ側のわきの下のリンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されておらず動く、もしくは、がんの大きさが5cm以上でリンパ節や他の臓器への転移はない |
|
ⅢA期 |
がんの大きさが5cm以下で、同じ側のわきの下のリンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されていて動かないか、リンパ節が互いに癒着している、またはわきの下のリンパ節には転移はないが胸骨の内側のリンパ節には転移がある もしくは、がんの大きさが5cm以上で、同じ側のわきの下または胸骨の内胸のリンパ節に転移がある |
|
ⅢB期 |
がんの大きさやリンパ節への転移があるかないかに関わらずしこりが胸壁に固定されていたり、がんが皮膚に出たり、皮膚がむくんだり、皮膚が崩れているような状態になっている。しこりのない炎症性の乳がんもこの病期から含まれる |
|
ⅢC期 |
がんの大きさに関わらず、同じ側のわきの下のリンパ節と胸骨の内胸のリンパ節の両方に転移ある、または鎖骨の上下にあるリンパ節に転移がある |
|
Ⅳ期 |
がんの大きさやリンパ節転移の状況にかかわらず、他の臓器への転移(骨、肺、肝臓、脳などへの遠隔転移)がある |
ステージ0期
ステージは非浸潤がんか、あるいはパジェット病できわめて早期のがんです。
がん細胞が乳管や小葉の中にとどまる乳がんで、適切な治療を行うことで転移や再発をすることはほとんどないと考えられます。
・パジェット病とは
パジェット病は乳がんのひとつです。
乳管にできたがんが乳頭の皮膚にできて、赤くはれ、ただれた状態になります。
しかしパジェット病は、乳管の壁を突き破ってまわりの組織に広がることはあまりないのでリンパ節転移はなく予後も良好な乳がんです。
治療は乳房切除術が基本となり、がんが乳頭と乳輪の付近にとどまっていることがわかれば、放射線治療と組み合わせた乳房温存療法が可能です。
センチネルリンパ節生検を念のために行って、転移があるかないかを確認するのが大切です。
センチネルリンパ節は、わきの下のリンパ節の入り口で、ここに転移があるかないかを生検検査で調べます。
この生検がリンパ節までを切除するかどうかの判断材料となります。
ステージ0期の治療
腫瘍の範囲が小さいと考えられる場合には乳房温存手術をします。
範囲が広い場合には乳房全切除術が必要になります。
がんの状態によりセンチネルリンパ節生検を行い、術後には放射線療法を行います。
非浸潤がんであれば小さな転移がある恐れも少なく、多くの場合には術後の薬物療法も必要としません。
ホルモン受容体陽性乳がんの場合には、乳房温存手術の後にタモキシフェン(抗がん剤)を5年間内服するという治療の選択肢もあります。
ステージⅠ期〜ⅢA期
ステージⅠ期
がんの大きさが2cm以下で、リンパ節や他の臓器に転移していない状態です。
ステージⅡA期
がんの大きさが2cm以下で、同じ側のわきの下のリンパ節は固定されておらず動く、もしくは、がんの大きさが2cmを超え5cm以下で、リンパ節や他の臓器への転移はない状態です。
ステージⅡB期
がんの大きさが2cmを超え5cm以下で、同じ側のわきの下のリンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されておらず動く、もしくは、がんの大きさが5cm以上でリンパ節や他の臓器への転移はない状態です。
ステージⅢA期
がんの大きさが5cm以下で、同じ側のわきの下のリンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されていて動かないか、リンパ節が互いに癒着している、またはわきの下のリンパ節には転移はないが胸骨の内側のリンパ節には転移がある。
もしくは、がんの大きさが5cm以上で、同じ側のわきの下または胸骨の内胸のリンパ節に転移がある状態です。
ステージⅠ期〜ⅢA期の治療
1.がんが比較的小さい場合
がんの大きさが比較的小さくて、広い範囲に石灰化が広がっていない場合には乳房温存手術が可能となります。
がんが乳頭に近くても乳房温存手術ができることもあります。
乳房温存手術を選択した場合には、原則的に術後放射線療法が必要になります。
手術後の薬物療法は必要に応じて行います。
2.がんが比較的大きい場合
がんが比較的大きくて温存手術が困難と考えられた場合には、乳房全切除術を行います。
ステージⅠでもマンモグラフィで広い範囲に石灰化があったり、CTやMRI検査で乳房内にがんが大きく広がっていると考えられる場合には乳房全切除術を行います。
がんが大きい場合には、術前に薬物療法であらかじめがんを小さくしてから手術を行うこともあります。
3.腋窩リンパ節(えきかリンパ節)の切除
腋窩リンパ節と呼ばれるわきの下のリンパ節への転移がある場合には、リンパ節郭清(リンパ節かくせい)と呼ばれるリンパ節を切除する手術が行われます。
また、手術で切除した組織を検査してがんの広がりや性質を調べ、必要に応じて薬物療法を行います。
4.手術後の薬物療法の選択
ホルモン療法や分子標的治療、抗がん剤治療を行います。
ステージⅢB期・ⅢC期
ステージⅢB期
がんの大きさやリンパ節への転移があるかないかに関わらずしこりが胸壁に固定されていたり、がんが皮膚に出たり、皮膚がむくんだり、皮膚が崩れているような状態。しこりのない炎症性の乳がんもこの病期から含まれます。
ステージⅢC期
がんの大きさに関わらず、同じ側のわきの下のリンパ節と胸骨の内胸のリンパ節の両方に転移がある、または鎖骨の上下にあるリンパ節に転移がある状態です。
ステージⅢB期ⅢC期の治療
局所進行乳がん
局所進行乳がんで乳房表面の皮膚や胸壁にがんが及んでいる、炎症性乳がんとなり、鎖骨上リンパ節にまで転移が及んでいるといった場合には、身体のどこかに転移を伴う可能性が高くなる。
このステージでは主に薬物療法で治療を行い、乳房のしこりや腫れていたリンパ節が縮小したなどの効果がみられた場合には、手術や放射線療法などの局所治療を追加することを検討します。
ステージⅣ期
がんの大きさやリンパ節転移の状況にかかわらず、他の臓器への転移(骨、肺、肝臓、脳などへの遠隔転移)がある状態です。
遠隔転移は乳房から離れた身体の場所にがん細胞が広がった状態です。
ステージ Ⅳ期の治療
このステージでは全身に転移のある乳がんとして薬物治療を行います。
がん細胞が全身のどこに広がって行き、潜んでいるかわからないため、がん細胞を根絶するのは難しく、目にみえる遠隔転移のがんを手術で切除したとしても、目に見えないがんは身体のどこかにひそんでいて、そのうち増殖してくると考えられます。そのため全身に向けて薬剤治療をします。
身体に対しての負担が大きいので通常では遠隔転移に対しての手術は行いませんが、原発病巣に対して疼痛、出血、感染などがある場合には、手術、放射線などの局所療法を行うこともあります。
>乳がんの疑いがある方はこちら
(無痛のMRI乳がん検診ができます)
乳がん生存率は
生存率とは、診断から一定期間の後に生存している確率のことを生存率といい、生存率のデータを集めることは治療効果を判断するための重要な指標となります。
なかでも5年生存率はほかのがんとの部位別生存率を比較する場合の指標としてよく使われます。
しかし、生存率はあくまでも比率であり個々の患者さんの余命には個別差があります。
がんの発生した場所や診断されたがんの進行の度合いにより5年生存率は変わっていきます。
乳がんの5年生存率
乳がんの5年生存率はステージ0では100%となり、早いステージで診断を受け、治療すれば高い確率で完治します。
しかし、ステージⅣで発見された場合の5年生存率は、38.7%に低下します。
乳がんの10年生存率
乳がんは、生存率が高いがんですので、10年生存率という指標もよく用いられます。乳がんの10年生存率はステージ0では100%と、早いステージで診断を受け治療すればこちらの生存率も5年生存率と変わりません。
しかし、ステージⅣで発見された10年生存率は、19.4%に低下します。
乳がんは早期に発見し治療することが重要です。
痛みゼロ、露出ゼロ、被ばくゼロの「無痛MRI乳がん検診」の5つのメリット
最近では、痛くない、見られない乳がん検診が広まっているのをご存知ですか?
「無痛MRI乳がん検診」と呼ばれるもので、乳房を圧迫される痛みや見られる苦痛もなく乳がん検診を行う方法が話題を呼んでいます。
「無痛MRI乳がん検診」(ドゥイブス・サーチ)には、痛みがなく、見られないだけではないメリットが他にもたくさんあります。
ここではその検査の特徴やメリットについても詳しく説明します。
無痛MRI乳がん検診とは
無痛MRI乳がん検査は、聞き慣れない検査の名前だと思いますが、簡単に言うと(造影剤を使わない)MRI検査で乳房の中身を診る検査のことです。
今までのスタンダードな乳がん検診で使われる機械は、エックス線を用いたマンモグラフィー検査でした。
それがMRIというドーム型の機械に入って、乳房の形にくり抜かれたベットにうつ伏せに寝てるだけで済んでしまう、今までに比べて格段に負担の少ない乳がん検診の方法です。
無痛MRI乳がん検診の5つのメリット
MRIで乳がん検診を行うことによって大きな5つのメリットがあります。
・検査の痛みがゼロ
・検査着やTシャツを着たまま検査が受けられるので露出ゼロ
・磁気を使った検査で被ばくゼロ
・乳がんを高確率で発見できる高性能
・乳房手術後でも検査可能
検査の痛みがゼロ
無痛MRI乳がん検査は乳房型にくりぬかれたベッドにうつ伏せになって行います。
マンモグラフィー検査のように乳房を挟まないので痛みがありません。
この検査の方法であれば自然な形で乳房が下垂するため、乳房の大きさに関わらず大きく鮮明に撮影できます。
乳房の自然の形そのままで圧迫しないので、乳房が挟まれる痛みは全くありませんから安心です。
検査着やTシャツを着たまま検査が受けられるので露出ゼロ
マンモグラフィやエコー検査は乳房を露出して撮影されますが、検査だから仕方がないとはいえ、ストレスや恥ずかしさを感じる方も多いでしょう。
MRIは磁気の力を利用して体の臓器や血管を撮影する検査なので、検査着やTシャツを着たまま受けられます。
また、技師と受診者が近接する時間は入退室時のみで、プライバシーが守られるので安心して受けられます。
磁気を使った検査なので、被ばくゼロ
マンモグラフィは、エックス線を使用するので微量ですが被ばくしますが、MRIの内部は磁石とコイルでできていてエックス線を使用しないため、被ばくが「完全にゼロ」であるという特徴があります。
そのため安心して繰り返し検査を行うことが可能です。
乳がんを高確率で発見できる高性能
無痛MRI乳がん検診の最大の特長のひとつはがんを容易に発見できることにあります。
無痛MRI乳がん検診のがん発見率は1000人あたり14.7人で、平均的なマンモグラフィの5倍以上に相当します。
70歳ぐらいでは、乳腺が萎縮してきて乳房のほとんどは脂肪となります。
その状態でマンモグラフィ検査をした場合には乳房は透き通って見えるのでがんは見つけやすくなります。
しかし、50歳ぐらいまではだいたいの方は乳腺が豊富に存在し、これがマンモグラフィでのエックス線を通しにくくなり乳房の中央部が白く写ります。
マンモグラフィの場合、がんは白く写るので白い絵に白い雪を描くようなもので、当然がんが見つかりにくいのです。
日本人女性は高濃度乳房と呼ばれる方が多いのですが、この高濃度乳房ではマンモグラフィでのがんの発見率は下がります。
Radiologyという画像診断で最も権威の高い科学雑誌でも、透き通っている乳房と、白く曇っている乳房ではがんの発見率が倍も違うことをレポートしています。
無痛MRI乳がん検診ではがんが黒く写りますのでマンモグラフィでは見分けにくいがんが発見できますから発見率が格段に違い高いのです。
無痛MRI乳がん検診は、このように乳腺の量に左右されにくいためがんの発見率が下がることはなく乳がんを高確率で発見できる高性能な検査です。
乳房手術後でも検査可能
乳房手術には大きく分けて、乳がん手術の場合と豊胸術の場合がありますが、乳がんの場合は手術で切除したところにインプラントを入れて形を整え、豊胸術の場合は乳房の両側にインプラントを入れます。
インプラントは強く圧迫すると破裂して炎症などを起こし、整えた乳房が変形してしまうおそれがありますので乳房を圧迫してしまうマンモグラフィーは行うことはできません。
エコー検査は、乳房を強く圧迫することはないので検査はできますが、インプラントの後方が見えにくくなるので検査自体を断られ受診できないケースもあります。
MRIではインプラントの種類によっては少しアーチファクトという邪魔な信号がでますが、多くは検査可能です。
無痛MRI乳がん検診ではインプラント挿入後の方も撮影できるので対応できます。
無痛MRI乳がん検診で快適に検診を
いままでの常識をくつがえした痛くない乳がん検診は、今までの乳がん検診が苦痛だった人には快適な方法です。
そんな無痛MRI乳がん検診ができる施設はこちらになります。
まとめ
乳がんはがんの進行度合いにより、病期をステージごとに分類しています。
乳がんの病期を分類しステージで表記することで、手術や薬物療法などをはじめとした治療方針を決め、生存率をはかるうえでわかりやすい指標となっています。
病期分類はされた乳がんのステージは0〜Ⅳ期に分類されます。
ステージ0期で乳がんが発見されることで5年、10年生存率は100%と高くなります。
病期ステージは乳がんの治療方針を決めるうえで欠かせない指標となるため、病状説明の際にも必ず話題にあがります。
乳がんの患者さんは乳がんの病期分類であるステージ分類を覚えておくと医師の説明がよりわかりやすいものになるでしょう。
>乳がんの疑いがある方はこちら
(無痛のMRI乳がん検診ができます)
参考文献
国立がん研究センター東病院 乳がんについて
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/breast_surgery/050/051/index.html
がん10年生存率58.3% に―国立がん研究センター調査
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00874/は
患者さんのために乳がん診療ガイドライン2019年版
https://jbcs.xsrv.jp/guidline/p2019/guidline/g4/q19/
乳がんの予後右と左で異なる? Care net
https://www.carenet.com/news/general/carenet/54868
乳がんのステージ 東京医科大学病院
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/cancer/breast/stage.html
乳がん 国立がん研究センターがん情報サービス
https://ganjoho.jp/public/cancer/breast/treatment.html#anchor1