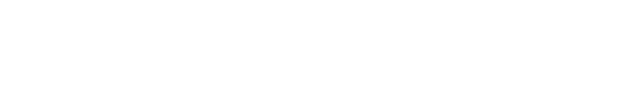早めの対応で心に健康を|うつ病の原因・診断・治療について
心の病気のなかでもメジャーな疾患であるうつ病。日本人の15人に1人がかかるとされ、心の風邪と呼ばれることもあります。
また、子どもから高齢者まで年齢や性別を問わず発症するリスクがあり、良くなったり悪くなったりを繰り返す人や入院治療が必要な人までさまざまです。そのため早めに対応し心を適切な状態に保つことが大切とされています。
本記事ではうつ病の原因や症状、治療方法についてわかりやすく解説します。
\予約制なので待ち時間ゼロ/
(お薬は最短で翌日配送できます)
うつ病とは?
うつ病はさまざまな要因で脳の神経伝達物資のバランスが悪くなり、気分や感情、意欲をコントロールできなくなったために発症する病気です。
精神的・身体的症状が長期間にわたって継続すると、社会生活が困難になり、重症化・慢性化してしまうリスクもあります。またその頻度も多く、日本では生涯に約15人に1人、過去12ヶ月間には約50人に1人がうつ病を経験しているといわれています。
うつ病の主な原因
うつ病を発症する原因は1つとは限りません。
一般的には以下にあげるさまざまな因子が複雑に関係して、うつ病を発症すると考えられています。
- 本人の性格・気質
- 性別
- 生活習慣
- 人間関係
- 社会的役割の変化
- 喪失体験
- 病気
- ストレス
- 薬
- 妊娠・出産
また、最近の研究では、他の病気が引き金となりうつ病を発症してしまうこともわかっています。代表的な病気としては、双極性障害、適応障害、統合失調症などの精神疾患。脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患。認知症、甲状腺や心臓・腎臓・肝臓などの病気が挙げられます。
そのほかにも、ステロイドやインターフェロンなど薬の副作用でうつ状態になってしまうケースも多数報告されています。
うつ病の主な症状
うつ病の代表的な症状は“気分の落ち込み”や“ゆううつ感”です。
そのほかにも、うつ病は全身にさまざまな症状が現れます。うつ病の症状は表のように「精神症状」と「身体症状」の大きく2つにわけられます。
| 精神症状 | 身体症状 |
|---|---|
| ● 意欲がなくなる ● 無関心になる ● 気分が落ち込む ● ぼーっとすることが増える ● ネガティブ思考になる ● 口数が減る ● ミスや物忘れが増える ● 喜びや楽しみなどを感じにくくなる ● 不安が強くなる ● 焦りやイライラ感を生じる ● 飲酒やたばこの量が増える ● 身だしなみを気にしなくなる など |
● 頭痛 ● 胸のドキドキ ● 不眠や過眠などの睡眠障害 ● 食欲がなくなる ● 食べ過ぎてしまう ● 味を感じなくなる ● 胃腸の調子が悪くなる ● 下痢や便秘を繰り返す ● 性欲がなくなる ● 生理不順になる ● 腰痛 ● めまい ● 肩こり など |
うつ病の種類
うつ病にはいくつかの種類があります。代表的なものが「メランコリー型」「非定型」「季節型」「産後」で、これらのうつ病には確立された診断基準があり、治療や予後についても研究がすすんでいます。
ここでは「メランコリー型」「非定型」「季節型」「産後」それぞれのうつ病の種類について解説します。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| メランコリー型 | 典型的なタイプのうつ病。 気分が晴れない、朝早く目が覚める、自分を責めるケースが多い。 |
| 非定型 | よいことに対しては気分がよくなる傾向がある。 食欲は過食で、体重が増えたり、眠り過ぎたり、だるさを感じやすい。 |
| 季節型 | 特定の季節にうつ病を発症し、季節の移り変わりと共に改善する。 冬に日照時間が減り、セロトニンの合成が上手くいかなくなることで発症しやすい。 繰り返して発症するケースもある。 |
| 産後 |
産後4週間以内に発症する。 |
うつ病の診断について
うつ病の診断にはアメリカの精神医学会が定義した「DMS-5」のうつ病診断基準が用いられます。
以下の症状のうち、少なくとも1つある
- 抑うつ気分
- 興味または喜びの喪失
さらに、以下の症状を併せて、合計で5つ以上が認められる。
- 食欲の減退あるいは増加、体重の減少あるいは増加
- 不眠あるいは睡眠過多
- 精神運動性の焦燥または制止(沈滞)
- 易疲労感または気力の減退
- 無価値感または過剰(不適切)な罪責感
- 思考力や集中力の減退または決断困難
- 死についての反復思考、自殺念慮、自殺企図
引用:うつ病の新しい考え方
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhep/45/2/45_359/_pdf
うつ病はDMS-5のうつ病9つの診断基準項目のうち5項目以上がほぼ毎日、ほぼ1日中あてはまるかだけでなく、人間関係や仕事などに影響を与えているかなど、総合的に判断します。
\予約制なので待ち時間ゼロ/
(お薬は最短で翌日配送できます)
なお軽症・中等症・重症は以下のように判断されます。
| 軽症 | 診断基準9項目のうち、5 項目を概ね超えない程度に満たす場合で、症状の強度として、苦痛は感じられるが、対人関係上・職業上の機能障害はわずか な状態にとどまる。 |
| 中等症 | 軽症と重症の中間に相当するもの。 |
| 重症 | 診断基準9項目のうち、5項目をはるかに超えて満たし、症状は極めて苦痛で、機能が著明に損なわれている。 |
抜粋:日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.うつ病(DSM-5)/ 大うつ病性障害 2016 P10
https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/iinkai/katsudou/data/20190724-02.pdf
うつ病になりやすい人の傾向
うつ病を発症する原因は1つではありません。さまざまな原因が複雑に関係し、あるきっかけで発症してしまうケースが多いのです。
さらに、うつ病になりやすい人にはいくつかの傾向や特徴があることがわかっています。順に解説します。
1.持病がある
持病のない人のうつ病の発症率は10.3%、10人に1人程度です。
しかし特定の持病を抱えている人は、持病のない人よりも高い確立でうつ病を発症しやすいことがわかっています。代表的な疾患とうつ病発症率は以下のとおりです。
| 病名 | うつ病発症(%) |
|---|---|
| 心疾患 | 17~27 |
| 脳血管疾患 | 14~19 |
| 悪性腫瘍 | 22~29 |
| アルツハイマー病 | 30~50 |
| 慢性疼痛をともなう身体疾患 | 30~54 |
2.家族歴
家族に気分障害や精神疾患を患った人がいる場合には、うつ病などの発症率が高くなるという報告があります。
3.生活歴
患者の成長・発達、学業の成績・学歴、職歴、婚姻歴、親子・友人・同僚などさまざまな人間関係がうつ病の発症リスクを高めることが示唆されています。
4.ストレス因子
うつ病を発症するきっかけに、何らかのストレスが関係していることは少なくありません。
うつ病の発症リスクを高めるといわれている代表的なストレス因子は、以下のとおりです。
大切な人との死別
破産やリストラ・失職などの経済的破綻
被災・罹災
重い病気の発症 など
5.睡眠状況
うつ病を発症した人の約85%に不眠があったという研究報告があります。そのほかにも眠りが浅くなったり、細切れになったりという特徴も報告されています。
うつ病を治療すべき理由と治療方法
うつ病の改善には、各個人の病状に合わせて、適切な時期に適切な治療を行うことが欠かせません。もしうつ病のサインを見逃し、放置してしまうとどうなってしまうのでしょうか?また、具体的にはどのような治療をするのでしょうか?
ここからは、うつ病の治療について詳しく解説します。
うつ病を放置するとどうなる?
うつ病は症状が多岐にわたるため、自分がうつ病であると気づかなかったり、精神科への受診のハードルの高さから症状が進行するまで治療を受けていない人も多いのが実情です。そのため、適切なタイミングで適切な治療を受けられていない人も多いとされています。
では、適切な治療を受けずにうつ病を放置すると、どうなってしまうのでしょう。うつ病は比較的軽症な段階で介入を行えば、十分症状の改善が見込める病気です。しかし、適切な治療をしていないとうつ病の症状は少しずつ強くなります。
その結果、仕事や人間関係が上手くいかなくなるだけではなく、最悪の場合自死を選ぶ人もいます。また、進行してしまった場合には、治療もうまくいかないケースも多く、症状が慢性化しなかなか良くならなかったり、生涯に渡って治療が必要になったりすることもあります。そのため、早期診断と早期治療が大切です。
自分がうつ病かもしれないと思ったら
もしも、自分がうつ病かもしれないと思ったら、素直に症状や自分の気持ちを受け止め病院を受診しましょう。うつ病のサインに早く気付いて治療することが、早期回復にはかかせません。
身近な人がうつ病かもしれないと思ったら
もし身近な人が落ち込んでいたり、ミスが目立つようになったり、いつもと様子が違うことに気づいたら無理をしていないか声をかけてあげてください。
多くの人がうつ病であることに気づいてなかったり、受診するきっかけがなかったりします。
あなたの一言が、大切な人を救うきっかけになるかもしれません。
うつ病の治療
うつ病の治療は大きく以下の3つにわけられます。
- 休養
- 薬物療法
- 認知行動療法
それぞれの治療について順に解説します。
1.休養
うつ病を発症している患者さんの“脳”はとても疲れています。十分な休養を取り脳を休ませてあげることが、回復の第1歩です。また、休養と言ってもただ休めばいいのではありません。
うつ病の発症の原因となった、仕事や人間関係などのきっかけから、心理的にも物理的にも離れる必要があります。自宅では十分な休養がとれない場合には、入院して休養をとるのも治療方法の1つです。
2.薬物療法
薬物療法とは薬での治療のことです。具体的には、脳の神経伝達物質を調整したり、緊張を和らげたり、眠りやすくしたりなど、さまざまな働きの薬を併用して治療します。
うつ病の薬の多くは、少しずつ症状が和らいでいくという特徴があります。患者さんの中には効果を実感できず、治療を辞めてしまったり、自己判断で薬を増やしてしまったりするケースがあります。
自分で薬を調整すると想定外の副作用が現れたり、薬の効果が弱まってうつ病が酷くなったりすることが報告されています。かならず医師の指示に従って服用しましょう。
\予約制なので待ち時間ゼロ/
(お薬は最短で翌日配送できます)
3.カウンセリング・精神療法
カウンセリングや精神療法は専門家のサポートを受けながら、うつ病を発症するきっかけになりやすい“考え方”や“性格”のくせを改善し、少しでも生きやすくするために行われます。
認知行動療法や森田療法などを通して、うつ病を重症化させない・再発しないような考えや行動ができるようにします。
まとめ
うつ病は誰でも発症する可能性がある病気です。一般的に治療を始めても、数日でよくなることは少なく、長期的な治療の継続、症状のフォローが必要です。なかには、生涯に渡って付き合っていかなくてはならない人もいる病気です。
今回解説した症状をもとに、もしも、あなた自身そして身近な人が「うつ病かもしれない」、そう感じたら、ぜひお気軽に当院へご相談ください。あなた自身、そしてあなたの身近な人の心の健康を守るために、スタッフ一同全力でサポートします。
参考資料
日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.うつ病(DSM-5)/ 大うつ病性障害 2016
https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/iinkai/katsudou/data/20190724-02.pdf