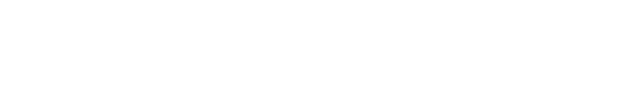「もしかして…」と思ったら。コロナ初期症状を詳しく解説!
新型コロナウイルス感染症が引き起こす初期症状は、いわゆる風邪の症状と区別がつきづらいといわれています。そのため「熱っぽい」「のどが痛い」などのちょっとした体調不良を感じるだけで、「もしかして新型コロナに感染してしまったのでは」と不安になる人も少なくありません。
この記事では、新型コロナウイルス感染症にかかったときに現れる初期症状の特徴をはじめ、似ている病気や新型コロナウイルスの感染が疑われるときの対処法などを紹介していきます。体調不良を感じるけれどどうすればいいのか分からないときに、ぜひ参考にしてください。
目次
1.初期症状では風邪との区別もつきづらい。特徴的な症状に注目を
【まめクリニック診療メニュー】
~急な発熱や体調不良もご相談ください~
平日22時迄・土日祝日診療のご予約はこちらから
24時間診療web予約はこちら
◆新型コロナウイルス感染症診療はこちら
発熱等の方への保険診療PCR検査
初期症状では風邪との区別もつきづらい。特徴的な症状に注目を
新型コロナウイルス感染症は、変異株の種類によって違いがあるものの、多くは3~5日間程度の潜伏期間を経て発症します。
ただし発症したばかりの時期は、「頭痛がする」「熱が出てきた」「のどが痛い」など、一般的にいう風邪と同様の症状が多くみられます。
そのため新型コロナウイルス感染症なのかそうでないのかの区別がつきづらく、症状だけで判断するのは困難です。
また、症状の程度によっては発症したことに気づかない人も存在し、さらにまったく症状が現れない無症状の人もいます。
新型コロナウイルス感染症と風邪やインフルエンザなどとの違いは、潜伏期間や症状が続く日数、発熱の有無、熱の高さなどです。
新型コロナウイルス感染症に特有の症状として「嗅覚障害」や「味覚障害」が出ることはよく知られていますが、オミクロン株では発生頻度が下がっています。
つまり嗅覚や味覚に異常がないからといって、新型コロナウイルス感染症ではないと判断することはできません。
すでに出ている症状が新型コロナウイルスによるものなのか、インフルエンザなのか、それとも風邪なのかを知るには検査が必要です。
少しでも感染が疑われる場合は、すみやかに医師や相談窓口に相談してください。
風邪とも似ている新型コロナウイルス感染症の初期症状
感染初期に見られる症状
新型コロナウイルス感染症の初期症状は年齢によって多少の違いがありますが、主なものは次の通りです。
|
症状 |
症状が出る人の割合 |
|
発熱 |
約2人のうち1人 |
|
せき |
|
|
頭痛 |
|
|
のどの痛み |
約5人のうち1人 |
|
下痢 |
|
|
鼻水 |
約13人のうち1人 |
|
味覚障害・嗅覚障害 |
約3~10人のうち1人 |
「食べ物や飲み物の味がしない」という味覚障害、「においを感じない」という嗅覚障害は、新型コロナウイルス感染症の大きな特徴として広く知られている症状です。
体調不良と同時に味覚や嗅覚にも異常を感じた場合は、新型コロナウイルス感染症の疑いが強いといえます。
ただし、味覚障害や嗅覚障害がどの程度の頻度で出るかははっきりしておらず、3~10人に1人とデータによってばらつきがあります。
さらにオミクロン株の感染では発生頻度が低いことも留意しておかなくてはなりません。
一方で、味覚障害・嗅覚障害をのぞく諸症状は、多くの人がかかったことのある風邪と酷似しています。
これらの症状だけでは、新型コロナウイルス感染症なのか、それとも風邪やほかの病気なのかを見分けることはほぼ不可能です。
さらに、新型コロナウイルスに感染したすべての人が何らかの体調不良を感じるとは限りません。
中にはまったく体調不良を感じない無症状の人もいます。
ただし本人が無症状でも感染力はあるため、知らず知らずのうちに他人に感染させてしまう可能性があります。
1900年前後にニューヨークで腸チフスが流行した際、その感染源となったのは発病していない女性でした。
無症状の場合、自覚がないまま周囲の人に病気を広げてしまう危険性をはらんでいます。
経過とともに見られる場合がある症状
まずは、新型コロナウイルスに感染すると経過とともにどのような症状が現れるかを知っておきましょう。
現れる頻度が高く、多くの人が経験する一般的な症状は次の3点です。
- 熱
- せき
- 倦怠感
一部の人に影響を与える可能性のある症状とされているのは、次の通りです。
- 味覚障害
- 嗅覚障害
- 鼻づまり
- 結膜炎
- のどの痛み
- 頭痛
- 筋肉や関節の痛み
- 皮膚の発疹
- 吐き気
- 嘔吐
- 下痢
- 悪寒
- めまい
また、比較的重い症状には次のようなものがあります。
- 呼吸困難
- 食欲減少
- 錯乱
- 胸部の持続的な痛みや圧迫
- 38°C以上の高熱
そのほか、稀に現れる症状としてあげられているものがこちらです。
- 過敏性
- 錯乱
- 意識の低下
- 不安
- うつ
- 睡眠障害
- 脳卒中
- 脳の炎症
- せん妄
- 神経の損傷
このように、新型コロナウイルス感染症の症状は多岐にわたります。
また風邪やそのほかの病気と似た症状も多く、症状をチェックするだけで原因を特定することはかなり困難であることがわかります。
新型コロナ感染症の潜伏期間は? どのような経過をたどる?
新型コロナウイルス感染症の潜伏期間は1~14日程度であり、実際には5日程度で発症することが多いといわれています。
ただしオミクロン株は潜伏期間が2~3日と短めで、7日以内に発症することが多いのが特徴です。
つまり発熱やせきなどの症状が出て、結果的に新型コロナウイルス感染症だと診断された場合、数日前にはすでに新型コロナウイルスに感染していることになります。
新型コロナウイルスは、人間の目や鼻、口の粘膜から体内へと入り込み、増殖しながらのどから気管支、肺へと下りていきます。
その過程で「のどの痛み」や「鼻づまり」といった風邪によく似た症状のほか、「嗅覚障害」「味覚障害」などを発症するというわけです。
感染して発症した場合、軽い症状が出るのみで治っていくのか、それとも悪化していくかの分かれ目となるのは、発症から7~10日目です。
この時期になると体内で免疫ができて新型コロナウイルスに打ち勝てるようになり、風邪によく似た諸症状が治まっていきます。
同時に感染力も著しく低下し、他人に感染させてしまうこともなくなります。
新型コロナウイルスに感染して発症した人のうち、およそ80%の人はそのまま回復します。
流行中のオミクロン株に症状の特徴はある?
新型コロナウイルスはこれまでに幾度も変異し、そのたびに変異株が生まれ、ニュースでも取り上げられてきました。
このうち2021年から2022年にかけて発生したのが「オミクロン株」です。
オミクロン株は2021年に急拡大したデルタ株よりも感染力が高く、下気道(気管・気管支・肺)よりも上気道(鼻から喉まで)に強い症状が出るという特徴があります。
具体的な症状としては、従来の新型コロナウイルスと同様に「せき」「頭痛」「疲労感」「鼻水」「発熱」が多くみられ、特に大きな違いは「のどの痛み」の症状を感じる人が多いことです。
オミクロン株に感染した人のうち、のどの痛みを訴える人は約53%と過半数を超しています。
これに対し、オミクロン株の前に流行したデルタ株でのどの痛みを訴えた人は約34%にとどまり、のどの痛みの出る割合が約1.9倍に増えています。
その一方で、新型コロナウイルス感染症の大きな特徴である「嗅覚障害」や「味覚障害」は、オミクロン株では減少しました。
割合でいうとオミクロン株では13%、デルタ株では34%と、かなりの差があります。
そのほか、発熱やせきの症状はオミクロン株が若干多く、疲労感や倦怠感はオミクロン株でもデルタ株でもほぼ同程度となっています。
また、オミクロン株にはいくつかの亜系統が存在します。
2022年初頭から起こった感染拡大の「第6波」では「BA1」や「BA2」系統が主流で、のどの激しい痛みを訴える人が多いのが特徴でした。
その後オミクロン株は「BA5」系統への置き換わりが急速に進み、その影響によって2022年6月頃から「第7波」が到来しています。
「BA5」系統による第7派の感染拡大期では、「38℃以上の高熱」や「倦怠感」といった症状を訴える人が多い傾向があります。
また「鼻水」や「せき」といった症状を訴える人も少なくありません。
さらに、症状が続く期間にも違いが出ています。
BA1では平均4日間だったのに対し、BA5は平均7日間と、やや長めです。
BA5に感染し発症した場合は、療養期間が長期間になる可能性が高いでしょう。
万が一の感染に備えて食料品や日用品などを準備をする際は、このことを見越しておくことをおすすめします。
新型コロナ感染症と似ている病気
風邪、インフルエンザとの違いは?
新型コロナウイルス感染症と並んでかかりやすい感染症といえば、「インフルエンザ」です。
これはインフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症で、毎年12月頃から3月頃の寒い時期に流行することでよく知られています。
インフルエンザにかかった場合も、風邪や新型コロナウイルス感染症と同様に「発熱」や「せき」といった症状が出ます。
インフルエンザは一般的に症状の出方が激しく、かなりの高熱を伴いますが、誰もが絶対にそうなるというわけではありません。
したがって、症状を観察するだけでは、風邪なのかインフルエンザなのか、それとも新型コロナウイルス感染症なのかを判断することは困難です。
病気の原因を特定するには、病院や検査機関で検査をする必要があります。
すみやかにインフルエンザの抗原検査や新型コロナウイルス感染症のPCR検査を行い、診断してもらいましょう。
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ、風邪の主な違いはこちらです。
|
新型コロナウイルス感染症 |
インフルエンザ |
風邪 |
|
|
発熱 |
37.5℃以上の熱が4日程度続く |
38℃以上の高熱 |
37~38℃程度 |
|
主な症状 |
せき のどの痛み 鼻づまり 倦怠感 嗅覚障害 味覚障害 |
せき 鼻水 のどの痛み 頭痛 関節痛 筋肉痛 倦怠感 |
鼻水 鼻づまり くしゃみ せき のどの痛み |
|
症状の現れ方 |
ゆるやかだが急激に重症化する |
急激 |
比較的ゆるやか |
|
潜伏期間 |
1~14日間 |
1~3日間 |
2~4日間 |
|
治癒までにかかる時間 |
1週間程度 |
1週間程度 |
4~5日 |
|
病原体 |
新型コロナウイルス |
インフルエンザウイルス |
200種類以上のさまざまなウイルス |
|
検査方法 |
PCR検査 |
抗原検査 |
なし |
ただし症状には個人差があります。
年齢や持病の有無などによっても違ってくるため、すべての人がここで紹介したケースに当てはまるとは限りません。
体調に不安を感じたときは自己判断せず、すみやかに医師に相談してください。
子供の場合はこんな病気にも留意を
子供がかかりやすい病気にも、新型コロナウイルス感染症と似た症状が出るものがあります。代表的なものは次の通りです。
- RSウイルス感染症
- ヒトメタニューモウイルス感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
この中でも「RSウイルス感染症」や「ヒトメタニューモウイルス感染症」といった病気は、「発熱」「せき」といった風邪によく似た症状が出るため、症状だけでは新型コロナウイルス感染症なのかそうでないのかを判断できません。
子供が体調不良を訴えたときは、なるべく早めにかかりつけ医を受診し、対処する必要があります。
「ヘルパンギーナ」は38℃を超える高熱が出やすく、口の奥に水ぶくれができ、のどの痛みがあるのが特徴です。
「手足口病」は微熱とともに手・足・口の中に発疹ができます。
さらに、これらの病気と新型コロナウイルス感染症の両方に同時にかかってしまうこともあります。
新型コロナウイルスのオミクロン株は、子供にも感染が広がっていることが懸念されています。
陽性者によくみられる症状は「せき」「たん」「苦しそうに呼吸をする」などです。
発熱が長引くことも多く、幼児の場合は高熱を出したことによる「熱性けいれん」や「意識障害」を起こしてしまうケースもあり、油断はできません。
さらに発熱による脱水症状にもなりやすく、注意が必要です。
「コロナかな?」と思った時の対処法
新型コロナ感染症が心配な時の対応フロー
「のどが痛い」「熱が出てきた」など体調に異変を感じ、新型コロナウイルス感染症が疑われるときはまず、普段から受診しているかかりつけ医に電話で相談をしましょう。
かかりつけ医での受診や検査が可能であれば、そのまま指示に従って診療や検査を受けてください。
このとき電話での連絡をせず、直接医療機関を受診することは控えるように厚生労働省からアナウンスされています。
感染拡大を防止する観点からも、まずは電話で連絡をしましょう。
かかりつけ医がない場合や夜間休日などで受診できない場合は、自分が住んでいる各自治体の相談ダイヤルに電話をします。
連絡先の電話番号は、各自治体の公式Webサイトに掲載されています。
相談のうえで新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、受診が必要となった場合は、診療や検査が可能な医療機関の紹介を受けてください。
PCR検査の結果、陽性だったときは症状や状況に応じて「自宅療養」「宿泊療養」「入院」などをすることになります。
陰性だった場合(新型コロナウイルス感染症ではなく、別の病気だった場合)は、必要に応じて医療機関を受診するか、もしくは自宅療養で様子をみましょう。
コロナ流行下で広がるオンライン診療
新型コロナウイルスの流行により、直接顔を合わせる必要のない「オンライン診療」が広がっています。
オンライン診療とは電話やスマホを使って医療機関に相談や受診ができるシステムで、診察手順は次の通りです。
受診したい医療機関(かかりつけ医や近くの医療機関)がオンライン診療を実施しているかどうかを確認する
オンライン診療の予約をする(予約方法は医療機関によって異なり、電話の場合は保険証などの情報を伝える)
予約時に支払い方法の確認をする
診療時間になったら電話やスマホで医療機関からの着信を受ける
本人確認
診療と症状の説明
医師の判断に従う
オンライン診療は便利なシステムですが、必ず診断や薬の処方がされるとは限りません。
オンライン診療後、医療機関での受診をすすめられた場合は、必ず直接足を運んで診療を受けてください。
オンライン診療で処方された薬を配送してもらう場合は、まず医療機関にどこの薬局で薬を受け取るかを伝えます。
そのうえで診療後に薬局へ連絡を入れ、薬を配送してもらってください。
場合によっては服薬指導のために来店を求められることもあります。
【まめクリニック診療メニュー】
~急な発熱や体調不良もご相談ください~
平日22時迄・土日祝日診療のご予約はこちらから
24時間診療web予約はこちら
◆新型コロナウイルス感染症診療はこちら
発熱等の方への保険診療PCR検査